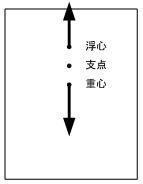
結局1時間ほど頑張ったところで寒さに耐え切れず断念した。そのときはどうすることもできなかったが、どうすべきだったろうかと反省を含めて凧について考えた。
トラブルシューティングの基本として、まず、現象を正確に把握することだ。どう飛ばなかったのか:一瞬揚がるのだが、すぐにくるくると回転してしまう。それに対して実施した施策:凧の下の方に重し代わりの厚紙をつけたが、意味なし。原因の究明:ここからが本題だ。
凧の正面から見て、凧に働く力は重力と浮力がある。浮力は揚力とも言うが、ここでは浮力と呼ぶことにする。重力は常に地面に向かって働く。浮力は風と凧の位置関係によって向きは変わるが、凧は常に風を正面から受けるし、糸によって角度が制限されているので、凧に対して常に一定の向きに働くとしよう。これらの力が、糸の中心のところ(糸目)が支点となって働いていると考えられる。
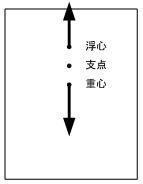
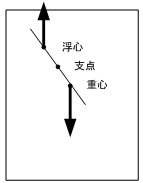
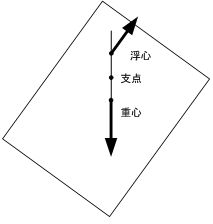
では、どうすれば良いのか?
実のところ、浮力は凧に対して常に一定の向きに働くとは言ったが、「頭の方に」とは言っていない。浮力のベクトルは、もしかしたら凧に対して斜めに向いてるのかもしれないのである。こうなると話はややこしい。しかし、よく考えてみよう。
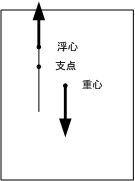
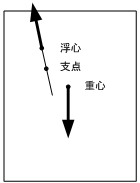
おいおい、それってどこだよ、というツッコミは多々あると思う。浮力は、微妙な歪みによって大きく変化してしまうから、もの凄く精度の高い工作でないと、計算で出すことはできないのだ。それではどうしようもないから、とりあえず浮力∝面積∝重さと考えて、重心の位置を参考にして設定するようである。しかし、これは目安でしかない。上の仮説によれば、はっきり言って重心のことなどどうでもよい。浮心とそのベクトルが知りたいのだ。
それには、風の無い室内で凧をぶら下げて、すっと上に持ち上げてやれば良い。この方法だと、重力の影響を受けないで浮力の方向を見定めることができる。何度かやってみて、最適な支点の位置になるように糸目を左右に振ってやればよい。細かく調整できるように、左右の糸の1本を自在結びにしておくと良いだろう。
糸目を調整する他に、もうひとつの手としては、浮心の位置を調整するという手もある。凧のどこかに小さなフラップをつけて、左右の浮力を変化させることによって浮心の位置が移動する。糸目をがちがちに結んでしまってどうしようもなければそうしよう。
よく長い尻尾をつけて調整しようとするが、それによって調整できるのは重心の位置である。上記理論によれば、凧の重心など無意味といっていいのだが、重心の位置をより下の方に下げることで確かに安定性は高くなる。しかし、凧が空に舞い上がるためには、重力以上の浮力が働かなくてはならないわけで、浮力による回転を止めるほどの重力を求めて長い尻尾をつけようとすると、決して飛ばない凧しかできないというわけだ。
ひとつの結論が出たところで、さらなる疑問も湧いてくる。